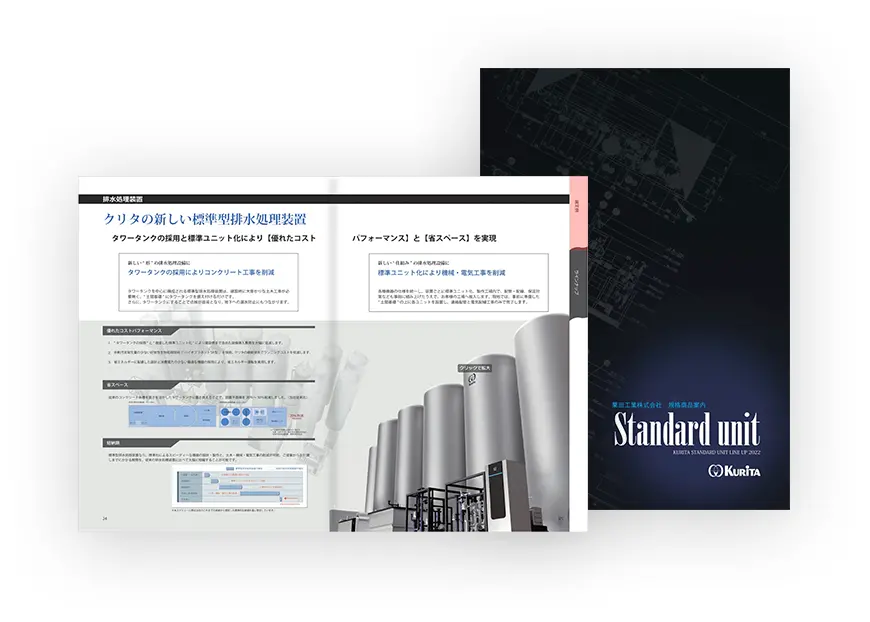水処理解説コンテンツを探す 検索結果
全選択を解除する
126
件 該当しました
並び順
-
水処理教室

RO膜(逆浸透膜)とは
容器内の液体と周りの液体との濃度が違い、薄いほうから濃いほうへ水が膜を通過して移動する現象を正浸透現象といいます。 この場合と逆方向に水を流す、逆浸透現象を応用して作ったRO膜(逆浸透膜)について解説します。
-
水処理教室

連続式電気脱イオン装置
栗田工業/KCRセンターの小川です。№9の水処理教室では、「連続式電気脱イオン装置」についてお話いたします。従来のイオン交換装置は、一定量の純水を採水した後、イオン交換樹脂に吸着しているイオンを薬品で除去しなければなりません。その除去作業やコストを低減するために開発された連続式電気脱イオン装置について解説いたします。
-
水処理教室

水道水をつくるための水処理
栗田工業/KCRセンターの坂倉です。№10の水処理教室では、「水道水をつくるための水処理」についてお話いたします。水道水の取水源は川の表流水、伏流水、地下水です。こうした取水源の水質は年々悪化しており、浄水場では高度な水処理技術が必要になっています。今回は、安心安全な水道水をつくるための水処理技術について解説いたします。
-
水処理教室

汚濁物質に合わせた処理方法の使い分け
栗田工業/KCRセンターの佐藤です。№11の水処理教室では、「汚濁物質に合わせた処理方法の使い分け」についてお話いたします。一般的に汚染物質は、大きさによって浮遊物質(1~100μm前後)、コロイド物質(1nm~1μm前後)、それよりもっと微細な溶存物質の3つの形態に分かれます。その処理方法を種類別に分かりやすく解説いたします。
-
水処理教室

凝集処理
栗田工業/KCRセンターの池上です。№12の水処理教室では、「凝集処理」についてお話いたします。自然界に存在する微細粒子は、一般的にマイナスに帯電しているため、互いに反発して凝集しません。そこで、プラス荷電をもつ凝集剤を添加すると中和され凝集が起こります。その凝集の方法などについて分かりやすく解説いたします。
-
水処理教室

加圧浮上装置
栗田工業/KCRセンターの小川です。№13の水処理教室では、「加圧浮上装置」についてお話いたします。水より比重が軽い物質というと油が代表的です。このような比重の小さい物質を水面に浮かせて分離する方法を浮上処理と言います。しかし、水と比重の差が非常に小さい物質では空気を加圧して浮上させる方法を使います。その時に用いる加圧浮上装置について解説します。
-
水処理教室

純水よりはるかに純度が高い超純水
栗田工業/KCRセンターの坂倉です。№14の水処理教室では、「純水よりはるかに純度が高い超純水」についてお話いたします。純水は溶液中の電解質を対象に計測しますが、超純水は電解質はもちろん水中に溶解している有機物、生菌、微粒子などが一定基準以下であることが求められます。ここでは特に半導体で必要な超純水について解説いたします。
-
水処理教室

超純水製造装置のしくみ
栗田工業/KCRセンターの佐藤です。№15の水処理教室では、「超純水製造装置のしくみ」についてお話いたします。半導体製品の洗浄や、半導体製造に使用する薬品の希釈用などには、他と比較的できないほどの高純度の超純水が必要です。今回は、水処理のすべての技術を投入して開発された超純水製造装置のしくみについて解説いたします。
-
水処理教室

純水製造装置のしくみ
純水の製造には、カチオン交換樹脂とアニオン交換樹脂をそれぞれ独立した塔に充填する多床塔方式と、両方の樹脂を均一に混合して一つの塔に充填する混床塔方式があります。このうち2床3塔で構成される多床塔方式について解説いたします。