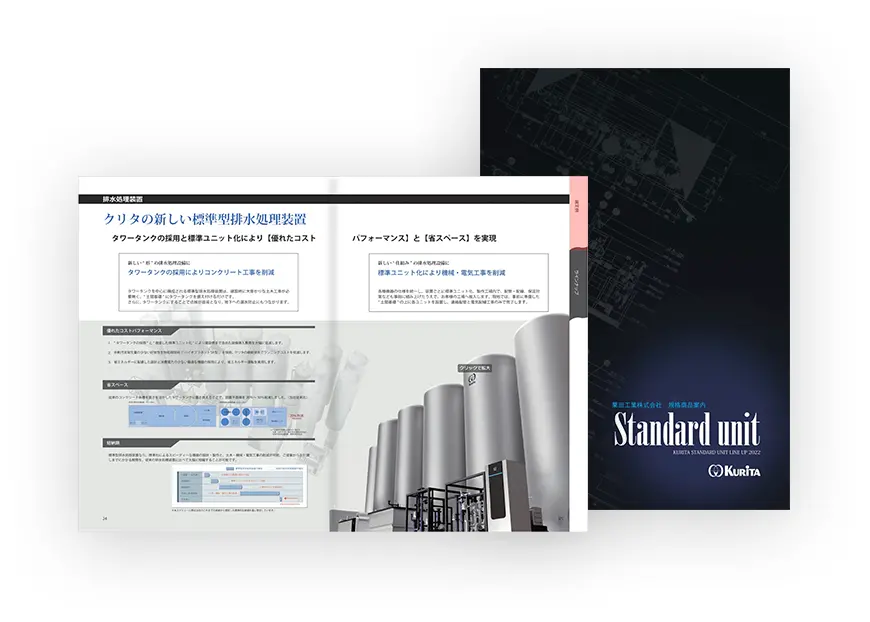水処理解説コンテンツを探す 検索結果
全選択を解除する
126
件 該当しました
並び順
-
水処理教室

冷却水系の『スライム障害』とは
主に大気開放されている冷却水の系統で、微生物が代謝物として生成した粘質物が、土砂等の無機物質を取り込んで軟泥状のスライムを形成することがあります。スライムが、熱交換器に付着すると、熱伝導率が低下してエネルギーロスが発生したり、散水板・ストレーナーの閉塞による運転停止につながることがあります。今回はスライムによる障害とその対策について解説します。
-
水処理教室

冷却水系の『スケール障害』とは
スケール障害は、冷却水に含まれる硬度成分(マグネシウムやカルシウム)やシリカ等が、冷却塔における水分の蒸発や伝熱面での加温等により析出(スケール化)することで発生します。析出したスケールは、熱交換器や冷却塔内部、配管等に付着し、熱交換効率の低下によるエネルギーロスの要因になるほか、ポンプ圧の上昇、流量の低下等設備の安定運転を妨げる要因にもなります。今回は、このスケール障害とその対策について解説します。
-
水処理教室

冷却水系で発生する障害の種類 ―腐食障害―
栗田工業KCRセンターの梶原です。腐食障害は、金属が水と酸素の存在下でさびとなる事、それにより配管などの厚みが薄くなる事に起因して発生します。冷却水系を構成する熱交換器や配管などが腐食すると、設備寿命の低下や補修費用の発生、漏水等による設備の運転停止など、多大な損失につながります。今回の水処理教室では、冷却水系における代表的な障害の一つ「腐食障害」について、腐食の反応機構や対策の考え方を解説します。
-
水処理教室

冷却水の水処理を行う必要性
栗田工業KCRセンターの梶原です。産業における冷却プロセスや空調設備には、冷却用の水(冷却水)をよく使います。冷却水の系統は、水に起因する各種障害が発生するので、効率よく、安定して稼働させるためには、水処理薬品による冷却水の処理が効果的です。今回は、冷却水の水処理によって得られるメリット、水処理薬品を使用する上で重要なポイント等を解説します。
-
水処理教室

膜を使った前処理方法
栗田工業/KCRセンターの佐藤です。№7の水処理教室では、「膜を使ったろ過」についてお話いたします。砂ろ過など、通常の前処理では微細な濁質が残ることがあり、そのまま製造工程で使用すると様々なトラブルを起こしてしまいます。そこで、砂ろ過を通り過ぎる微細な濁質を除去するために膜が開発されました。そのしくみを解説いたします。
-
水処理教室

水道水をつくるための水処理
栗田工業/KCRセンターの坂倉です。№10の水処理教室では、「水道水をつくるための水処理」についてお話いたします。水道水の取水源は川の表流水、伏流水、地下水です。こうした取水源の水質は年々悪化しており、浄水場では高度な水処理技術が必要になっています。今回は、安心安全な水道水をつくるための水処理技術について解説いたします。
-
水処理教室

汚濁物質に合わせた処理方法の使い分け
栗田工業/KCRセンターの佐藤です。№11の水処理教室では、「汚濁物質に合わせた処理方法の使い分け」についてお話いたします。一般的に汚染物質は、大きさによって浮遊物質(1~100μm前後)、コロイド物質(1nm~1μm前後)、それよりもっと微細な溶存物質の3つの形態に分かれます。その処理方法を種類別に分かりやすく解説いたします。
-
水処理教室

凝集処理
栗田工業/KCRセンターの池上です。№12の水処理教室では、「凝集処理」についてお話いたします。自然界に存在する微細粒子は、一般的にマイナスに帯電しているため、互いに反発して凝集しません。そこで、プラス荷電をもつ凝集剤を添加すると中和され凝集が起こります。その凝集の方法などについて分かりやすく解説いたします。
-
水処理教室

加圧浮上装置
栗田工業/KCRセンターの小川です。№13の水処理教室では、「加圧浮上装置」についてお話いたします。水より比重が軽い物質というと油が代表的です。このような比重の小さい物質を水面に浮かせて分離する方法を浮上処理と言います。しかし、水と比重の差が非常に小さい物質では空気を加圧して浮上させる方法を使います。その時に用いる加圧浮上装置について解説します。